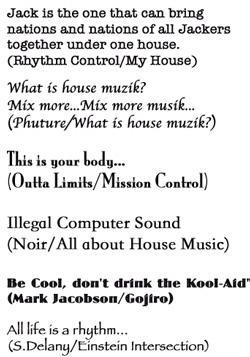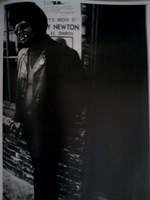帯を見て幼稚なサイケデリック賛歌だったら嫌だなあと心配したものの、読んでみたら表現という行為とそれが抱えるパラドックスを指摘した濃い内容ですた。
『金坂健二は、いまでは忘れられた存在に等しいが、60年代後半アングラ映画運動と鋭く過激な評論活動で、一世を風靡した人物。だが、内ゲバ的な内紛で疎んじられ、アングラ映画の流れをひくイメージフォーラムや、インディペンダント・シネマの世界から名前を抹殺されたアングラ映画監督だ。その経緯を書ける立場にボクはないので、その中味は今ははぶく。
ともかくも、「アングラ」という言葉は金坂健二と『映画評論』誌の映画評論家佐藤重臣が作ったようなもので、状況劇場や恋情桟敷が、代名詞のように思われている「アングラ」は、そもそもは「アンダーグラウンド・シネマ」から来ている。』風雅遁走より
葉隠れを連想させる宣言に始まり、60年代アングラ界隈の生々しい描写とアジテーションが繰り返されて、あとがきで自らのパラドックスを告白するという構成。あとがきに全てが詰まってると言っても過言じゃないです。
金坂氏は、かなり癖のある人だったらしく、商業作家はもちろん実験映画作家のほぼ全員から嫌われてたなんて噂もあるみたい。実力や功績の割には、資料も少ないしwikiにすら載ってないのはそのせいなのかなあ。アングラという言葉を薄めて「ポケットマネーで行う余興」や「ピーターパン症候群の鎮痛剤」程度に捉えていると間違いなく殴られますw
■全てに賛同しているわけではないけど、気になった箇所をメモ。
『トリップの核心は、いっぺん死ぬ、ということなのである。もちろん肉体は生きたままで、いままでの自分の一生によって形成されて来た<自己>がことごとく粉砕するのだ。』
『人間は日常の平面だけで、馬が草を喰って生きているように生きて行けるものではなく、芸術に関して"ロマンティック"でなくなった人間は、金儲けか、戦争か、どこか別のところ自己投機の場を見出すしかない。』
『デュシャンが"作品"は"作家"の意図や思わくと無関係に"後生"(posterity)によって評価されるというまでもなく、情報伝達力のスピードアップによって、芸術行為もいま、終わるまえから万人の共有物となってしまう。もともと幻覚剤による浮上状態を指した<旅>(trip)という言葉がいまや人間行為のほとんど何でもあてはまるのは、やや皮肉な見方をすると、すべてがいわば情報が通過するための媒体に逆算さてしまう現代社会の状況を反映している。情報という電波の嵐が通り抜けたあとには、かすしか、ジャンクしか残らない。ちょうどバロウズの描いたジャンキーが、静脈だけでなく舌や眼球にまでヘロインの通過した針跡を残しているように。』
『ほんとうに戦う人びとは、あるメディアのためにではなく、<未知の人間>のために戦うのだ。あらゆる既成のメディアは頽廃する、具体的には制度化され、機械と官僚の手にゆだねられる。たとえばテレビは、いまいったいどうなっているか。制度の範囲内で戦う、あるいはその黙認によって自分なりの意匠を咲かせる、ということにリアリティーのある時代もあった。だがいっぽうでは、"情報革命"が、いっぽうでは体制が------あるいはわれわれひとりひとりが-------その時代を殺してしまった。』
『日本の芸術家、いや世間で従来そう思われて通って来た連中の大半は、そろって工業文明機構の宣伝部みたいなものを形成しているのかも知れない。それで芸術諸ジャンルの区別の崩壊による"全体性の恢復"(!)などというセリフが出て来るのだから、まったく開いた口がふさがらないのである。』
『LSDを飲んだ人がほとんどいない日本では、ストロボライトと轟音と多色光線を駆使する新しい全体的な"環境"は人々を刺激しもうひとつの流行語"サイケ"が生まれたが、暗示的なことに、この言葉はひどく短命に終わった。いわゆるフーテン族を一方極におきながら、いっぱんの青年男女にまで原色の衣装がゆきわたりつつあったが、それはあくまで形だけの適応にすぎず、アメリカにおけるような、深刻な幻覚剤体験とか、それに伴う社会的な断絶がどこにもなかったのである。』
『戦闘のためのモラルにも、その美しさがあることはたしかだが、それは主として戦いが不利であるときにだけそういえるのであって、いったん、どんなに少しでも優位に立つと、それは<体制>そのものを作る。たとえば新聞部員につめ寄るときの彼らをロング引いて見たカメラは、まさにそのことを発見していた。』
『"アンガージュマン"が生存競争に参加にするということだったのは二十世紀芸術全般にいえることだが、とくに日本の近代化の末期のわれわれの高度工業化時代において、芸術家もまた実業家と同じよう激烈な生存競争の渦中にあるのだということが、ロマンチックに受け止められたのである。すべての戦闘のための思想は右翼と左翼とを問わず、そこに発している。そして現在の日本文化は、もしそれが存在するなら、いぜんとしてこの生存競争ロマンチシズムから一歩も抜け出ていない。芸術家も知識人も、"タフ"で"カッコ良く"能率的に量産しなければならない。極端ないい方をすれば、日本では優れた本とは発行部数の多い本のことだし、優れた作家とは自家用車を持っている連中である。こうした初歩的でしかもおそるべき荒廃があり、それに抗して発言するのもまた、間もなく同じ競争の渦中にあって、より良く闘うことだけを目指している自己を発見する。』
『テクノストラクチュアとは現代ではまず管理の構造であり制度であって、公募展—審査—授賞とは絵描きをヒエラルキーによって管理する伝統的な制度である。それが今日にいたるまで、なんと有効であることか!ぼくは加藤のように新しい人間がエエジャナイカ行進から生まれる人間であるとも信じないが、ともかく、最低自分の思ったことを正面向いて、いうべき場所で、いえる人間であって欲しいものだと思った。その点が変わらないかぎり、いくら現代芸術を唱えて見ても、それは部落民すなわち前近代人によって超近代が実戦される、ときわめて不条理な仮説—つまり絵に描いたもちにすぎない。』
『創造力の働きが仮に自由であったにせよ、それを働かす人間は、芸術家といえども社会の外には存在せず、彼の行為は、まったく社会的行為となるほかなかった。まして秩序は抜け目なく「発表」を制度化していたのだ。ここですでに、芸術の自由とその管理かされた発表システムという二重性は厳密には破産している。無関係性は幻影にすぎない。「作品」はそれが持っているはずの内的な、自由な価値や目的とは関係なく、史上に出されて売られることになる。(中略)幻想は売れない。いやむしろ幻想でも売れる。ただそれが温存され保護育成されるのは、あくまで生産と達成を至上命令とする社会機構のメカニズムへの潤滑油、アクセサリイとして無益無害である範囲において、だった。』
『だがきわめて巨視的に見たら、人間の杜会はこのようにして進むのであり、サブ・カルチュアであったものがカウンター・カルチュア(Counter Culture)にエスカレートし、さらにその位置をも越えてカルチュアの中心に進んで行くはずなのだ。優しげなビートルズの唄があれだけ世界の若者のハートを掴んだのも、それがこのような和合の状況を先読みしたハーモニーに溢れていたからなのだ。映画「イージー・ライダー」もそうなのである。コンテンツは凄惨な断絶に終わる。ハイウエイの朝露の上で、アウトローたちは鮮血にまみれ、バイクだけが天使の羽根のように飛ぶ。それはまさしく断絶のリリシズムだ。しかしそれを盛ったメディアムとしての映画は、機構によって配給され、人びとに利益をもたらした。しかもこの映画の集合的な性格、明るさ”新しさ”はこのことと無関係とはいえないのだ。トム・ウルフのような作者もまたケイシーらの、まったく解読しがたいだろう行動と世間との間で通訳のような、あるいは仲裁人の、役割を果すメディアなのだ。』
『体制のビックマシンは、芸術のスモールマシンが自転しても痛くもかゆくもない。だからこそ、そいつらをいっしゅの名物として自分の裏庭で遊ばせておくのである。』
※あとがきより
『書くことが、出版する事が矛盾である本、というのが、ぼくが自分に与えうる唯一の自負である
"作品"の破産を前提にして、一歩前進して、仮に芸術行為と呼ぶわれわれの行為の形態もまた、客観的に見れば、ある時間空間の制限内にある—つねに、何をやっても、逸脱し越境しようとだけ試みて来たぼくがいま、痛いほどそう感じる。
この制限は、まったく自分たちが現在の社会構造の中に生きている、というまぎれもない事実から生まれている。ひじょうに味もそっけなくいえば、"マーケット"ということなのだ。
いや、自分は自分の"芸術"の中でそれを越えているからいいのだ、というのが、万博以前の古式の考え方だった。この社会組織の中に生きつつ、それを"論理"で否定しているからいいのだ、という種のいい草は、まだまだポピュラーが。だが、生きた人間というのは、つねにその全身においてしか問題にできない。頭はどこか雲の上のほうにあって、手足はどこ、尻はマイホームの名kといったような使いわけは、許されないことがはっきりした。だからこそ、"作品"や、いかなる種類の弁証法にも逃げこむというこが、もはやできないのだ。
全生活を均等なメディアとしてしか、ぼくらには生きようがない—このもっともラディカルな実践とは、あたかも何もしないように見えることだろう。
こうして、ありうる芸術行為の形態は、しぜん<芸術の破壊としての芸術>になったのだが、どっこいそいつもまた、マーケットの制ちゅうを逃れて、その外側にとどくとは、いえないのだ。メディアの破壊としてのメディアなら、それじたい生産物(プロダクト)として、まさに破壊しようとしたシステムにアダプトされてその若返りのタネとなり、同じマーケット内で消費されて終わらない、という根拠がどこにもない。
ところが、ぼくは、およそ長く多く仕事した"作家"のすべてが、この陥穴に陥っていくプロセスばかり、執拗に見つめ、証言してたような気がする。
その作業じたいに一定に意義がないことはない、また繰り返すことには、意味がない。』
■美術手帖とSpectatorで、彼の特集が組まれたこともあります。特に美術手帖の方は70ページ近く割かれていて、デザインも素晴らしいので必読です。
<おまけ>
 ウォーホールと金坂
ウォーホールと金坂

 HAHCD-002
¥2000
HAHCD-002
¥2000 LR-002
¥1700
LR-002
¥1700 LR-001
¥1300
LR-001
¥1300